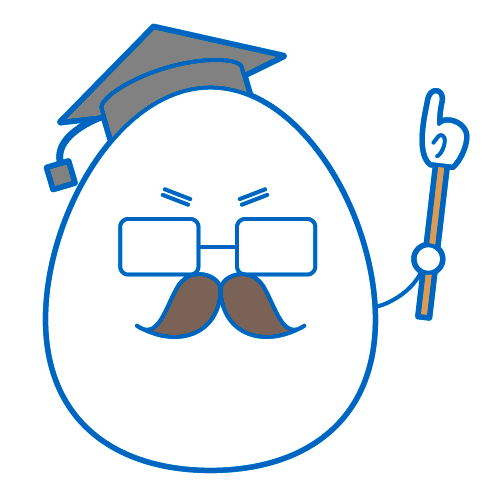-

-
抜管の基準、管理法
2016/4/25
★はっきりと決まった基準はなく患者ベースで決めるべきだが、ハイリスクの場合ステロイド使用を考慮する。 ■抜管前の確認事項●エアウェイの確保が可能なことを確認①意識状態よい;GCS<8, 指示動作可能②咳が十分可能;咳嗽時のpeak expiratory flow>60ml/min③痰の量 ...
-

-
ウィーニングとは何か、いつウィーニングするか
2016/4/11
★優秀な指標はあまりなく、原因治療が出来て酸素化がよく全身状態安定していれば、その場の判断でweaningを開始してよい。 ■Weaningとは●人工呼吸器による呼吸サポートを減らし、呼吸の大部分を自力で行うようにすること⇒徐々に減らす方法が一般的 急に減らす方法=spontaneous breat ...
-

-
放射線被曝って具体的にどれだけ身体に影響あるの?
2016/4/1
★先進国で、主にCTによる癌発症率上昇が問題となっている。 ■医療による放射線被曝●単位・電離放射線の濃度;R・電離放射線吸収量;Gy(グレイ)・部分的な被曝を全身被曝量に換算した値(実効線量);Sv(シーベルト) …医療のイメージングにおいては1Gy=1Sv⇒実効線量が被曝による悪影響の指標となる ...
-

-
無症候性心筋虚血にはPCIが良いのか
2016/3/25
★予後は悪いので、理想的な薬物治療でも虚血が誘発される場合、インターベンションを検討すべき。 ■無症候性心筋虚血の予後・負荷心電図でのST変化、シンチでの誘発虚血があるが、狭心症状がない患者 (安定狭心症患者の内、症状がないもの)⇒死亡率、ACS発症ともに悪い;心臓死は3〜6倍 …症状がある患者より ...
-

-
多変量解析の簡単な理論、やり方、結果の書き方/解釈
2016/3/7
★統計ソフトで簡単にできるが、結果の解釈が大事。 ■多変量解析の種類・重回帰分析:アウトカム(従属変数)が連続変数の場合・多重ロジスティック回帰分析:アウトカムが名義変数の場合※因子(独立変数)は、連続変数でも名義変数でもよい …名義変数の0,1は、そのまま連続変数の数字として適用される(ダミー変数 ...
-

-
3群以上になるとなぜt検定でなくANOVAを用いるのか;post-hoc analysisの適応
2016/3/4
★帰無仮説が異なるため。 ■理論的根拠●帰無仮説:A,B,Cのどの3群間にも差が無い・t検定を行った場合 …帰無仮説:2群間で差が無い =AとB, BとC, CとAの組み合わせで、5%有意水準で比較することとなる⇒結果は、それぞれ95%の確率で正しい⇒帰無仮説を満たす確率(p)は、1-(0.95)^ ...
-

-
正規性の検定はなぜ必要か;連続/名義変数の組み合わせによる分析法のまとめ
2016/2/29
★平均の比較は正規性を前提としているため。 ■変数の種類・名義変数:基本的に0か1・連続変数:連続的な値 ■正規分布・左右対称の釣り鐘型の分布(連続変数の話)…平均と分散がわかれば再現できる⇒正規分布同士の比較であれば、平均で比較すべき(パラメトリック検定) ・群のどれかが正規分布でなければ、平均で ...
-

-
コンタクトレンズを入れたままにすると何故失明するか;コンタクトレンズの合併症
2016/1/18
★物理的、アレルギー性に機械的損傷がおき、それをベースに感染性角膜炎を合併し、治療が遅れると失明しうる。 ■コンタクトレンズへの眼への影響・角膜と結膜の上皮細胞、涙液層により感染/傷害から保護されている⇒コンタクトレンズはこれらの相互作用、ガス交換などを阻害しうる※基本的にはコンタクトレンズは涙液層 ...
-

-
トロポニンの心筋梗塞でのカットオフ値は、CKD患者でどうなるか
2015/12/9
★Optimal Cutoff Levels of More Sensitive Cardiac Troponin Assays for the Early Diagnosis of Myocardial Infarction in Patients with Renal Dysfunction;C ...
-

-
安定狭心症の評価に冠動脈CTが良いか、シンチが良いか
2015/12/7
★Outcomes of Anatomical vs functional testing for CAD;NEJM APRIL,2 2015 ■Intro初発の安定した胸痛の患者は沢山いて、狭心症診断のため負荷シンチ/負荷心電図/負荷エコー(functional testing)をするが、陰性もか ...